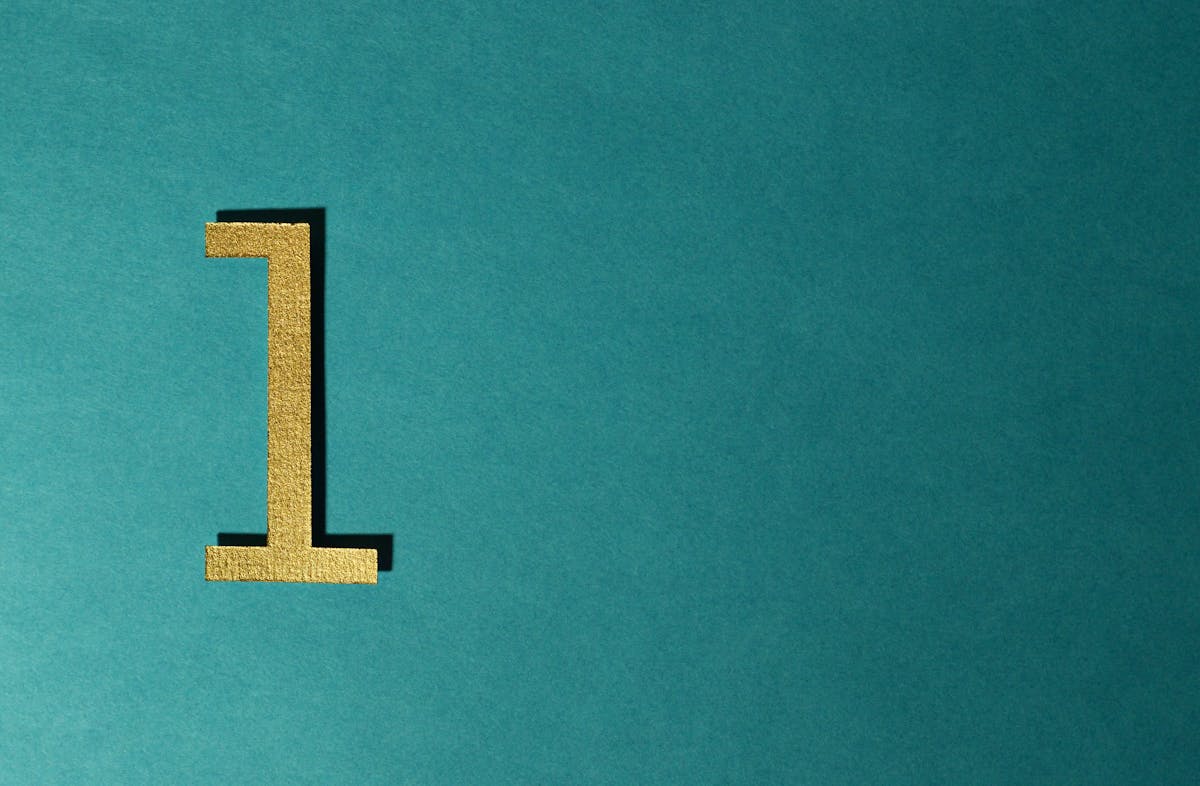*Please note that this page may contain some affiliate links.
※当ブログでは、アフィリエイト広告(リンク)を利用しています。
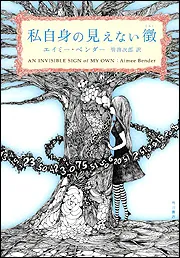
『私自身の見えない徴』
エイミー・ベンダー (著), 菅啓次郎 (訳), 角川書店, 2006年2月28日
感想と思考
「隣町で待ってるからね1)」。”いま”自分の周りにいる人たちにはそう言い残し、それでも私自身の時間軸を生きてゆくのだと、手を振り歩みを進めること。この本の主人公・モナはそれがいかに(寂しくも)尊いものであるかということを絡まる想いを抱えるリサに気がついてほしいがために、物語の終盤、あの寓話を手渡したのではないか、と私は思う。
私はそれを空中にむかってささやいた。とてもしずかに、ただ私たちふたりだけに聞こえるように。リサは私の脚の上で休み、手首をちゅうちゅう吸い、息づかいは整ってしずかだった。私ののどでは波が高まり、ふくらみ、私は掌をベンチに押しつけた。聞いて、と私は木にむかっていったーー私がいま話していることを聞いて。しるしをつけておいて。気づいて。2)
この物語はアメリカのどこか片田舎、けれど明らかだった都市名はなくあくまでも”架空の”町を舞台として始まる。けれどそれは私たちにとって壁一枚隔てられた遠いおとぎ話……というわけでは全くなくて、煌めくファンタジー要素のなかにはあきれるくらい現実的な、リアリティをも孕んでいる。
ひょんなことから小学校で算数を教えることになった、元・町一番の数学少女モナ(ただし現在は20歳の誕生日を迎えたところであるため「少女」と呼ばれる年齢は卒業している)。相手にする子どもたちは誰もがどこか、何かが複雑で、モナもその関わりにたいへん手を焼く。「数字の形のように見える、身近な『物』を教室へ持ってきましょう」という「数と物」の時間に、癌患者である母親の点滴チューブを持ってくるリサ。父親の腕のミイラを抱え、自信たっぷりに教卓へ立ったダニー。どこか生意気な様子ではあるけれど、やはり言葉にしきれない感情を胸に、きりきりと抱えているアン。
これら一人ひとりの特徴はまるで違うようだけれど、ひとつだけ確かな共通点がある。モナも含めこの皆は常に、「過去」をどうにかして抱きしめようとしている。手放さないように、決定的なあの時間へどうにか指を食い込ませたままでいられるように、惜しくもその場所へぶらさがったままでいようとする。げんにリサ自身も「木でできたものをこんこんとノックすること3)」以外のあらゆる、「好きだった行動」や「好きだったもの・こと」を、「止めること4)」を始めてしまう。今ここへ留まることを知らない「時間」に、それでも対抗するかのように。
けれどどんなに足掻いたとしても、時間とは不可逆的である。子が生まれやがて親が死に、子は寂しさを抱えながらも大人になる。もちろんその「順番をはずれて何かが失われるとき5)」だってざらにあるけれど、いずれにせよ育った子はやがて、「自分自身の人生」を生きようとすることは必至である。
別れを告げることは、寂しい。傷があろうともその生々しい温かさから身を引くことは、覚悟がいる。目前の幼いリサにはだから、まだそれは容易いことではないかもしれないけれど、それでもいつかこの”寓話”の意味に気のつく日がやってきてほしい。
物語を最後まで読み終えたとき、私たち読者は誰の目線で彼らのことを見つめているだろうか。今度は自身が幼子へ物語を手渡す番だと、一歩先からまなざしで包み込んであげることのできる日は、きっと来るのだろうか?
- 1) エイミー・ベンダー 菅啓次郎(訳) 2006 私自身の見えない徴 角川書店 pp. 306
- 2) 同上, pp.304
- 3) 同上, pp. 13
- 4) 同上, pp. 12
- 5) 同上, pp. 249-250